介護保険料っていつから徴収されるの?介護保険制度の仕組みや計算方法は?介護保険料がいつから徴収され、さらにその計算方法や、介護保険制度の仕組みやサービス利用の流れについて、まとめてみました!
公的介護保険制度とは?
介護保険制度とは、介護が必要となったと市区町村から認定を受けたときに、公的介護サービスを受けることができるサービスです。
公的介護保険の対象者
| 65才以上の方 | 第一号被保険者 | 介護状態となった原因を問わず、介護サービスを受けられる |
| 40~64才の方 | 第二号被保険者 | 16種類の特定疾病が原因の時に介護サービスを受けられる※ |
| 40歳未満の方 | 公的介護保険の対象外 | 公的介護保険の保障の対象とならない |
※16種類の特定疾病(第二号被保険者)
| がん(末期) | 関節リウマチ | 筋萎縮性側索硬化症 | 後縦靭帯骨化症 |
| 骨折を伴う骨粗鬆症 | 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管疾患に基づくもの) | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病) | 脊髄小脳変性症 |
| 脊柱管狭窄症 | 早老症 | 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群など) | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞) | 閉塞性動脈硬化症 | 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など) | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険サービスの流れ!
要介護認定を受けるまでの手続きの流れを見てみましょう!
1、申請…本人または家族が市区町村の窓口に申請
2、主治医の意見書
3、認定調査員による訪問調査
4、一次判定…2と3に基づきコンピューター判定
5、二次判定…介護認定審査会による審査
6、要介護認定
原則、申請から30日以内に結果通知が行われます。
公的介護保険のサービスは?

引用:https://kuku.lu/s32b96a
要介護認定による度合いに応じて「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分類されます。
在宅サービスの場合、介護サービスを利用できる限度額は、要介護度に応じて決定されます。
限度額の範囲内でサービス利用の場合、個人の負担は1割・所得が一定以上の第一号被保険者は2割・特に所得の高い層は3割負担となっています。
要介護度の目安と月額の支給限度額
| 区分 | 要介護認定の目安 | 支給限度額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 |
| 要介護5 | 日常生活遂行能力が著しく低下し、日常生活全般に介護が必要。意思伝達がほとんどできない。 | 360,650円 | 36,065円 | 71,130円 |
| 要介護4 | 食事に一部介助が必要。排泄、入浴等全般的な介助が必要。両足で立位保持がほとんどできない。 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 |
| 要介護3 | 食事や排せつに一部介助が必要。入浴など全般的に介助が必要。片足での立位保持ができない。 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 |
| 要介護2 | 食事や排せつに何らかの介助が必要。立ち上がり歩行などに何らかの支えが必要。 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 |
| 要介護1 | 食事や排せつなど、時々介助が必要。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られる。 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 |
| 要支援2 | 食事や排せつなど、時々介助が必要。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られる。この状態のうち介護予防サービスにより状態の維持や改善が見込まれる。 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 |
| 要支援1 | 入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 |
利用できるサービスは?
要介護1~5(在宅サービスを利用可能)
・在宅サービズ
| 訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの生活援助をしてくれるサービス |
| 訪問看護 | 病状安定後、医師の指示のもとで、看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助をしてくれるサービース |
| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス |
・施設サービス
| 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で在宅では介護が困難な人を対象とし、日常生活上の世話や機能訓練を受けるための施設
新規入所者は要介護3以上の人に限定 ※要介護1・2の人で認知症・精神障害等やむを得ない理由により介護路偉人福祉施設以外での生活が困難な場合に限り入所可能 |
| 介護老人保健施設 | 病状が安定した人が、看護や医学的管理のもとで介護、機能訓練等を行い、自宅復帰を目指す施設
入所基準は要介護1以上 |
| 介護療養型医療施設 | 急性期の治療を終え、長期療養を必要とする人が、医療や介護、日常生活上の世話を受ける医療施設
入所基準は要介護1以上 |
| 介護医療院 | 長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供する医療施設です
入所基準は要介護1以上 |
・地域密着型サービス
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間に定期巡回、臨時対応するなどの訪問介護サービス |
| 定期巡回
随時対応型訪問介護看護 |
訪問介護と訪問看護が一体的・密接に連携しながら、定期巡回と随時訪問で24時間365日対応するサービス |
要支援1・2(介護予防サービスを利用可能)
・在宅サービズ
| 訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの生活援助をしてくれるサービス |
| 訪問看護 | 病状安定後、医師の指示のもとで、看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話や診療の補助をしてくれるサービース |
| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス |
・地域密着型サービス
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間に定期巡回、臨時対応するなどの訪問介護サービス |
| 定期巡回
随時対応型訪問介護看護 |
訪問介護と訪問看護が一体的・密接に連携しながら、定期巡回と随時訪問で24時間365日対応するサービス |
・自立(非該当)
| 必要と認められた場合、市区町村の行う介護予防事業(認知症予防・転倒予防・栄養改善等)を利用可能 |
介護保険料いつから払う?65歳以上は?徴収方法は?
前述のとおり被保険者については、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分かれています。
そして40才に達したときから介護保険料を支払う事になり被保険者となります。
第1号被保険者・・・・65歳以上
基本的に年金から天引きされた保険料は住所地の市区町村に納め、介護が必要になったときにその市区町村から介護サービスを受けます。
第2号被保険者・・・・40歳以上65歳未満
加入している医療保険の保険者(健康保険組合・共済組合・国民健康保険組合など)の規定に基づいた金額を、医療保険の保険料と一緒に支払います。
40才の誕生日の前日を指し、その月から介護保険の第2号被保険者となります。例えば、4月1日生まれの人は、前日の3月31日が「40才に達したとき」となり、4月分から被保険者となり、その翌月からの支払いとなります。
民間企業の社員や公務員は、健康保険料・共済組合保険料と一緒に支払います。
この場合、39才以下の夫の扶養に入っている配偶者が40才以上の場合、配偶者は第2号被保険者となりますが介護保険料は徴収されません(健康保険組合によっては、「特定被保険者」として保険料を徴収される場合もあります)。
 |
【中古】不安解消!高齢者施設お金選び方入居の流れがわかる本 親の介護に限界を感じる前に知っておきたい! /翔泳社/太田差恵子 (単行本(ソフトカバー)) 価格:888円 |
![]()
介護保険料の計算方法は?
収める保険料は、第1号被保険者(65歳以上)か第2号被保険者(40歳から65歳未満)かによって変わります。
その計算方法については
・第1号被保険者(65歳以上)
世帯の課税状況および本人の前年の所得に応じて決まり、市区町村の定める基準額と保険料率をかけて算出されます。
・第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
加入している医療保険の保険者によって変わります。
・健康保険加入者
健康保険組合や共済組合の保険料の計算方法は、給与(報酬)や賞与に介護保険料率をかけて算出され、事業所と被保険者の折半です。
支払いは、健康保険の保険料と一緒に天引きされます。
介護保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×介護保険料率
標準報酬月額とは、給与などの報酬を段階分けしたもので、通勤交通費や残業代も含まれます。標準賞与額とは、3ヶ月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てたものです。 介護保険料率は健康保険組合によって異なります。
例えば、協会けんぽの場合で、標準報酬月額が30万円と仮定して、30万円×1.73%(介護保険料率)=5,190円で、さらに労使折半なので実際の負担はこの半分になります。
・国民健康保険加入者
市区町村ごとに、所得割、均等割、平等割、資産割の4つの組み合わせで計算され、介護保険料率も異なります。国民健康保険加入者には、労使折半がありません。
介護保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割
こんな記事も読まれています
介護保険料いつからで計算方法は?介護保険制度の仕組みについて!《まとめ》
介護保険は40才~65才までの第2号被保険者と、65才以上の被保険者に分類されます。
それぞれ適用になる内容が違います。
また介護認定も、要支援1から要介護5までに分かれ、受けれるサービス内容も異なってきます。
来たる未来の為、予備知識を持って臨みたいですね!



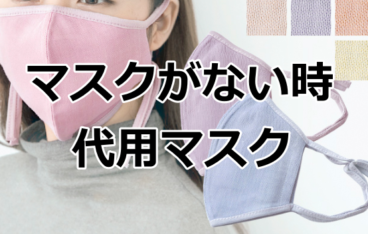

コメント